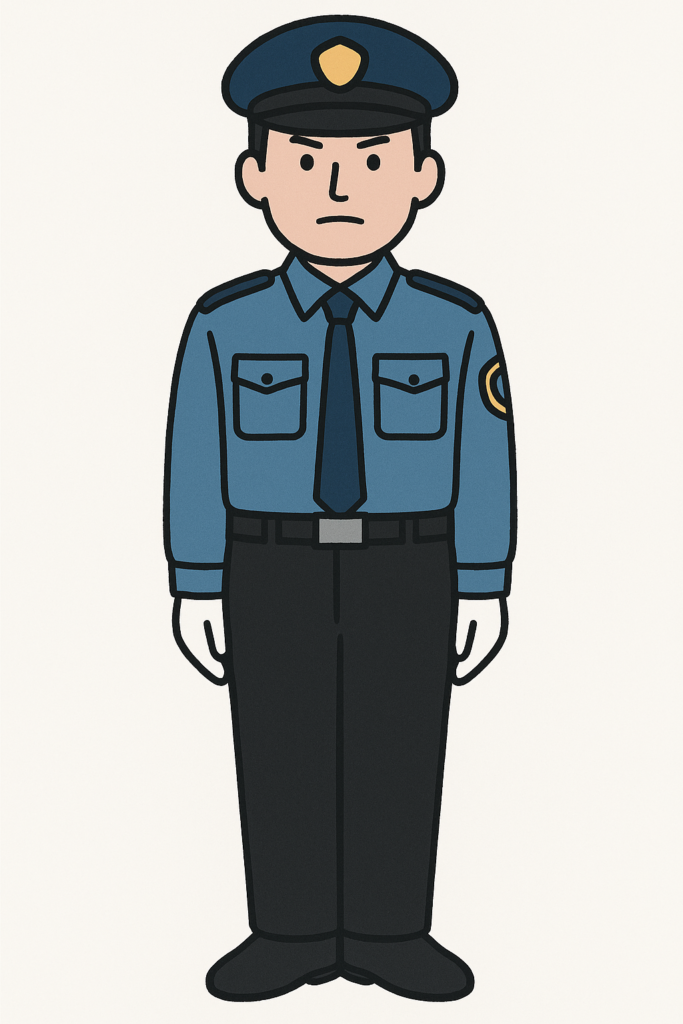
目次
警備員の仕事は誰にも感謝されない?
今週も警備の現場が終わった。朝から晩まで交通整理に追われ、誰からも「お疲れさま」と言われることはない。存在はまるで空気のように扱われ、むしろ空気の方がまだ重要だと感じることすらある。なぜなら、俺がいなくても現場は回ると思われているからだ。
特に今日はひどかった。作業員に「ちょっとどいて」とぞんざいに言われ、休憩中にもかかわらず立ち上がった瞬間、舌打ちされる始末。俺がいなければ、トラックの進行だってスムーズに行かないはずだ。それでも誰も感謝してくれない。寒さや暑さに耐えながら、歩行者に頭を下げ、交通の流れを管理する日々だ。
作業の責任も押し付けられる現実
終業後には「作業完了印」を記入する場面もあったが、責任者は「そこらへん書いといて」と軽く言い放っただけ。正式な手順を無視され、仕方なく自分で印を記入して現場を後にする。帰り道には虚しさがこみ上げ、これが本当に仕事なのか、それともただの時間の消費装置なのかと自問する。
誇りのない日々に積もる怒り

警備員として誰にも名前を覚えられず、感謝もされず、ただ立っているだけの毎日。無関心と軽蔑、そして安っぽいヘルメットのにおいだけが残る現場に、誇りを見つけることはできない。「食うために働く」ことにはもっと意味があるはずだと思っていた。多少の辛さがあっても、どこかに誇りがあるはずだと思っていた。しかし現実はそれとは程遠い。
辞めたい気持ちは敗北ではない
「辞めたい」と口に出すことは、これまで負けを認めるようで飲み込んできた。しかし、これは敗北ではなく、自分を守るための宣言だ。怒りがあるうちに抜け出す。自分をこんな扱いで終わらせない。怒りこそが、自分がまだ生きている証だからだ。








